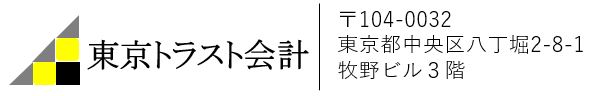インボイス登録が不要なケースとは?
Contents
インボイス登録は任意ですが・・・
インボイス登録を行うか否かは「任意」というのが制度上のルールとなっています。
従って、インボイス登録を行わないとしても何らルール違反にはならないのですが、これまでの解説記事の通り、多くの事業者でインボイス登録を迫られることが予想されます。
しかし、これまで消費税の申告を免除されていた事業者にとっては「可能であればインボイス登録を行わないでおきたい・・」というのが正直なところではないでしょうか。
今回は、インボイス登録を行わなくてもデメリットが生じない(もしくはデメリットが限定的な)ケースをご紹介します。
インボイス登録を行うか否かを迷われている事業者は今回の記事を参考に、自社に当てはまるものがないかをご検討いただければと思います。
ケース1:顧客が一般消費者のみ
インボイス制度は、端的に特徴を言ってしまうと、「インボイス登録を行っていない事業者への支払は消費税控除が制限される」という制度であり、取引の顧客側にデメリットが生じる制度です。
ここで、顧客が一般消費者のみである事業を行っている場合(例えば小売業など)、顧客側に消費税申告が必要とされませんので、消費税控除ができないというデメリットが生じず、結果として、インボイス登録を行わないという選択肢も生じ得ます。
補足すると、仮に自社が課税事業者である場合であっても(例えば基準年度(※基本的には2年前)の売上高が1000万円以上の事業者)、一般消費者のみが顧客であれば、同様の理由から、インボイス登録を行わないとこともあり得ます。この場合、消費税計算上のメリットはないですが、適格請求書発行事業者の登録番号を取得・管理するなどの事務負担が不要になるという利点があります。
ケース2:顧客が免税 or 簡易課税の事業者のみ
インボイス制度の抜け道をついたような形になりますが、制度の仕組みを踏まえると、顧客が一般消費者でなくても(つまり事業者であっても)、免税事業者または簡易課税事業者のみである場合にもインボイス登録しないことも選択肢になり得ます。
インボイス制度は「顧客側で消費税控除が制限される」というデメリットが生じる制度であるため、顧客が事業者であっても、それら事業者が「免税事業者」又は「簡易課税事業者」であれば顧客側に消費税の控除が必要ないためです。
ただし、顧客が免税事業者 or 簡易課税事業者であることを客観的に把握することはできませんので、顧客への確認や交渉が必要になるでしょう。
なお、1年間の売上高が5,000万円を超えている場合、そもそも免税事業者 or 簡易課税事業者となることはできませんので、売上高5,000万円を明らかに超える(超えてそうな)顧客がいる場合、残念ながらこのケースに当てはまる確率は低くなります。
ケース3:顧客の了解が得られる場合
繰り返しになりますが、インボイス制度は「顧客側で消費税控除が制限される」というデメリットがある制度です。
従って、顧客側がそのデメリットを受容し、免税事業者のままでいても従来の取引条件・価格を継続(あるいは若干の値引き程度で妥結)することに了解が得られるので場合は、インボイス登録を行わないことも十分考えられます。
もし顧客が数十社いるような場合、全ての顧客に了解が得られることはかなり難易度が高いと予想されますが、一方で、顧客が数社など限られている場合は、インボイス登録を行わないことができるか個別に交渉してみる価値があります。
インボイス登録しない場合の注意点
上記ケース1~3のいずれかに当てはまり、「インボイス登録を行わない」という判断を下した場合でも、将来的に営業面で不利に働く可能性があり得るという点には留意が必要です。
例えば、以下のような事例を見てみましょう。
・当社はケース3(顧客から了解が得られる場合)に当てはまったので、インボイス登録を行わないこととした。
・インボイス制度開始後、新しい候補顧客との商談。もう少しで商談がまとまりそうであるが、商談の最後で顧客から「インボイス登録の有無」を確認された。
・相見積先の競合他社はインボイス登録を行っており、自社はインボイス登録を行っていないことが判明
・提案内容では自社が勝っていたようであるが、インボイス登録を行っていない(顧客側で消費税控除ができない)ことが決め手となり、交渉は破談に・・・
上記はあくまで架空の事例ではありますが、to Bの事業を行っている場合で、今後も新規取引先の開拓を計画している場合は、この架空の事例に近い事例に出くわす点の可能性がある点も勘案したうえで、インボイス登録の是非を検討すべきです。
まとめ
今回は、インボイス登録が不要となる可能性があるケースとして以下を解説しました。
- ケース1:顧客が一般消費者のみ
- ケース2:顧客が免税 or 簡易課税の事業者のみ
- ケース3:顧客の了解が得られる場合
- インボイス登録を行わない場合の注意点
インボイス登録を行うか否かは、顧客の状況や顧客との取引関係、事業の計画によって判断が分かれます。
上記を踏まえてもインボイス登録を行うか迷っている・・・という事業者は、ぜひ当事務所にご相談ください。
絶賛インボイス制度のご相談を受付中です!
【こちらもチェック】
<驚きの料金>インボイスの前に確定申告書を税理士に頼んでみては?